こんにちは、里子です♪
昨年インスタで豆板醤が簡単に手作りできることを知り、絶対にトライしてみようと思い一年。
やっとこの季節がやってきました!
春になるとスーパーで見かけるそら豆。

豆板醤はそら豆を使って自宅で作ることができるんです♩
今回は豆板醤作りの様子をお届けします。
豆板醤のレシピ
今回参考にしたのはこのサイト↓↓

材料

・そら豆(さやから出した状態) 237g ←そら豆25本分
・乾燥麹(そら豆の重量の50%) 119g
・塩(そら豆の重量の20%) 48g
・韓国唐辛子(そら豆の重量の10%) 24g
・そら豆の煮汁 少量
※各グラム数はそら豆の重さから計算しています
麹はいつも塩麹や醤油麹を作っている無農薬の乾燥米麹を使いました。
唐辛子はただの粉唐辛子だけではなく粗挽き唐辛子も加えた方が風味はよくなるみたい。
私は持っていなかったので、タルコムの韓国唐辛子(甘口)のみを加えました。
事前準備
・豆板醤を入れる容器を熱湯消毒もしくはアルコール消毒する
私はパストリーゼで消毒しました。
パストリーゼは食品に直接噴霧可能なアルコール度数77度の除菌剤です。
・麹を細かくする(しなくてもオッケー)
包丁で切る、もしくはミキサーなどで細かくする。
・そら豆以外の材料を同じ器に量り入れて混ぜ合わせておく
作り方
① そら豆を処理する

茹でた後に薄皮を取りやすくするため、さやから出したそら豆に切り込みを入れる。
調べたら2パターンの処理方法がありました。
<パターン1>
黒い筋の下に横向きに切り込みを入れ、黒い筋を取りのぞく。

私はこの方法が楽でした。でも雑なのでそら豆自体も削れています。
<パターン2>
黒い筋の反対部分に、縦に切り込みを入れておく。

これもありだけど、パターン1の方がツルッと出てきました。

雑な分、切り取った部分が大きいからです。
② そら豆を柔らかくなるまで蒸す(熱湯のお鍋で茹でてもOK)


指で潰せるほどの柔らかさに蒸す。

10分蒸しました。
③ そら豆をよく潰す



私は食品に使えるビニール袋に入れて潰しました。
使ったのはこのビニール袋↓
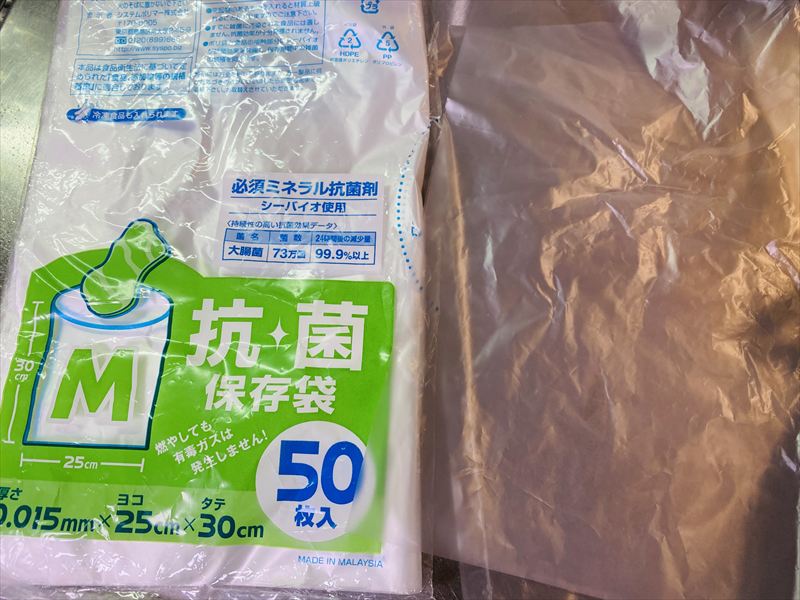
④ ③に残りの材料を全部入れてよくこねる。


パサパサしてる場合は茹で汁を加える。
私は大さじ3加えました。
⑤ 消毒済みの容器に詰める



空気が入らないようにギュッと詰めていく。

ラップをして、豆板醤とラップの間に空気が入らないように、
上からクッキングペーパーをたくさん詰めました。



完成!

作業はこれだけ。
日の当たらない常温で6ヶ月以上経ったら完成!
途中で混ぜる必要もありません。
豆板醤の別レシピ(味噌を入れる)
豆板醤のレシピを色々検索していると「味噌」を入れるものもチラホラ見かけました。
発酵好きな友人から連絡が来た際に「豆板醤作ったことある?」と聞くと、ちょうど私と同じ日に豆板醤作りのレッスンを受けてきたとのこと。
その際、味噌あり、なし、どちらも食べたけど、「味噌ありがコクがあって美味しかった」と教えてくれました。
調べると、次のような違いがあるみたい。
・味噌入り→コクが出て日本人好み
・味噌なし→スッキリとしていて辛さが際立つ
なので、私も味噌入りバージョンも作ってみました。
こちらは乾燥麹を粉砕せずそのまま混ぜてみました。
2回目のレシピ
今回参考にしたのは発酵×旬野菜のレシピを発信しているあやかさんです♪

・そら豆(さやから出した状態) 144g ←そら豆8本分
・乾燥麹 15g
・塩(そら豆の重量の20%) 22g
・韓国唐辛子(そら豆の重量の10%) 22g
・味噌(冷蔵庫の使いさしの米味噌)大さじ3/4
・そら豆の煮汁 大さじ1
※各g数はあやかさんのレシピを参考に計算しています

あやかさんのレシピはわかりやすいので、本も持っています!
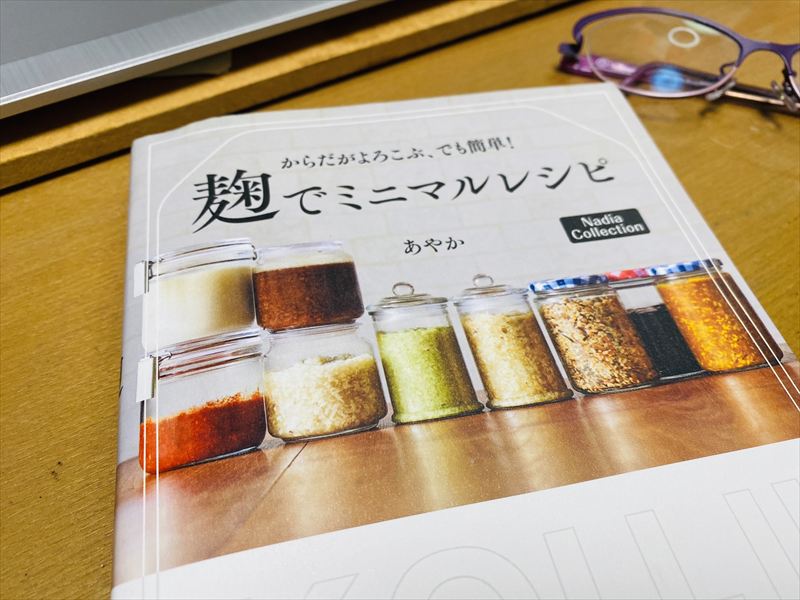
事前準備
・豆板醤を入れる容器を熱湯消毒もしくはアルコール消毒する
・そら豆以外の材料を同じ器に量り入れて混ぜ合わせておく
作り方
基本的に前回と同じです。

そら豆を蒸す

蒸している間に他の材料を量る

そら豆を食品保存袋の中でつぶす(写真撮ってないけど。。。)
ちなみに、そら豆の事前処理は、あやかさんはパターン②(黒い線と反対側に切れ込みをいれる)でされていたから私もパターン②で処理しました。
案外これもツルっとでてきて良かった!


つぶしたそら豆に他の材料を加えてよく混ぜあわせる



空気が入らないように瓶に詰める
完成!
瓶に詰める作業は、前回は手袋をつけて、少しずつ団子状にして、つぶして詰めたけど、今回はスプーンでしました。
詰め終わってからはラップのみで、上には広い空間も空いたままで放置。
はたしてどうなるのやら。
1回目に作ったものとカビの発生のしやすさなど比較してみます♪
作ってみた感想

写真左:作った日
写真右:2週間後
写真ではわかりづらいけど、2週間経つと土色っぽかったのが、赤味が強い色に変化しています。

発酵が進んでいる証拠です!
そら豆を買うのも調理するのも初めてだったけど、豆板醤作り自体はとっても簡単でした!
豆板醤の完成は6か月後なので、どんな味がするのかずっと楽しみ♪
このワクワクtimeが未来からの贈り物のようで、手作りをする醍醐味に感じます。
そうそう!
豆板醤は時間をおくほどに熟成が進んで美味しくなるらしいので、10年以上発酵させてもいいみたい。
どんな味か食べてみたいですね!
どんなものでも今の時代は検索すればレシピが出てくるけど、でも家庭で食べるものは本来どんなレシピでもOKなんだろうなーと思います。
腐敗しないように塩分濃度さえ守っておけば、少々独自のアレンジをしても大丈夫だと思っています。
※一般的に塩分濃度10%以上だと安心です

豆板醤は完成が早くて6か月後だからすぐには味見できないけど、
「この味が好みだわ♪」と思える豆板醤が作れるようになれたらいいなぁ。
でも私の家族は私以外辛い物は食べないので、消費するのは私一人・・・。

それにしても、そら豆ってあんなに大きなフカフカした鞘に守られているのに、入っているのは2、3粒だなんてまるで高級車!
カーク氏は次のように言っておりました。

そら豆と聞くと平和な感じがするけど、豆板醤はそれの対局にあるような感じがする。
たしかに!
可愛らしいツルッとしたそら豆が激しい真っ赤な辛い食べ物に変化するとは想像できないですよね〜。
6月は梅しごとをするのでまたレポします♪


